子育てコラム
山ちゃんの 子育てコラム集
「山ちゃんのブログ」に掲載した【子育てコラム】を集めてみました。
61 記録写真 05/17/2014 23:01:00

デジタル写真になってから、気楽に写真を撮ることが出来るようになりました。操作も簡単で誰にでも上手に撮れます。旅行や行事などの記録写真は良い思い出になります。
出来れば、子どもががんばってい姿を記念写真として撮られては如何でしょうか。 音読している姿、家事のお手伝いをしている姿、子どもが描いた絵や工作など色々なシーンがあると思います。
写真に撮ること自体、子どもにとっては、認められていると喜びます。がんばっている自分の姿をみて、自尊心も育まれます。
出来れば、子どもががんばってい姿を記念写真として撮られては如何でしょうか。 音読している姿、家事のお手伝いをしている姿、子どもが描いた絵や工作など色々なシーンがあると思います。
写真に撮ること自体、子どもにとっては、認められていると喜びます。がんばっている自分の姿をみて、自尊心も育まれます。
62 しつけ 05/18/2014 19:33:00

ある行動をした後に良いことが起こると、その行動は強化され、反対に悪いことが起これば、その行動は消去されます。叱るよりも誉める方が効果的にしつけが出来ると言われています。但し、時には叱ることも大切です。子どものめざしている目標が好ましくないもの、自分や相手を傷つけること、反社会的な行為に対しては、叱る必要があります。日頃から叱ることと叱らないことを区別しておくことです。子どもが小さい時には、口で教えるだけではなく、親が実際に見本を見せることが大切です。良い見本を見せることが出来ない場合は、好ましい行動を子どもと共同作業と思って、一緒に取り組むことです。
63 発達に合わせる 05/19/2014 22:42:00

『いやっ』という絵本があります。幼い子が「いやっ」の言葉を覚えて、なんでも「いやっ」の連続。その結果、ひとりぼっちで寂しさを味わい、「いいよ」の言葉を使ってもとの優しい子に戻るお話です。
2歳前後の子どもは「いやっ」といってお母さんの言うことに従わなくなります。この時期から自己主張をするようになるからです。
小学校三・四年生では、お母さんの意見より友達の意見を大切に考え、友達との関わりを優先して行動します。 子どもの発達時期の特徴によって問題が起こります。この時期に合わせてしつけの仕方を考えることも大切です。
ただ、子どもによって成長も違いますし、前進しては後退と乱調がああります。 しかし、長い目で見るとそれなりに成長しているのは事実です。
2歳前後の子どもは「いやっ」といってお母さんの言うことに従わなくなります。この時期から自己主張をするようになるからです。
小学校三・四年生では、お母さんの意見より友達の意見を大切に考え、友達との関わりを優先して行動します。 子どもの発達時期の特徴によって問題が起こります。この時期に合わせてしつけの仕方を考えることも大切です。
ただ、子どもによって成長も違いますし、前進しては後退と乱調がああります。 しかし、長い目で見るとそれなりに成長しているのは事実です。
64 言葉使い 05/20/2014 22:38:00

日常会話に不自由がなくなる頃、子どもは家庭内の言葉に関心がなくなり、友達が使っている乱暴な言葉やテレビなどの言葉に魅力を感じて使うようになります。
その言葉が下品であったり人を傷つける表現であっても、言葉の意味など何も理解していません。使って良いものかの判断もできません。
そこで、ひどい言葉を使っていた場合は、「その言葉は、人を嫌な気持ちにさせるチクチク言葉だから使いません」 「普通に使うのは〇〇です」と教えて下さい。 それでも止めない場合は、その言葉に反応しないで無関心を装って下さい。
その言葉が下品であったり人を傷つける表現であっても、言葉の意味など何も理解していません。使って良いものかの判断もできません。
そこで、ひどい言葉を使っていた場合は、「その言葉は、人を嫌な気持ちにさせるチクチク言葉だから使いません」 「普通に使うのは〇〇です」と教えて下さい。 それでも止めない場合は、その言葉に反応しないで無関心を装って下さい。
65 発達段階 05/21/2014 23:09:00

年齢によって体と心の発達が違ってきます。1歳後半から自己主張が出て来て対応に戸惑うことがあります。
2歳前半には自己主張が最高に達します。同時に甘えたい心と自立の心が同時に出ます。 「いや」「だめ」「自分でやる」と言った言葉が増えます。
2歳後半には、自己主張しますが、次第に感情を抑えることを覚えてきます。
3歳には、個性が出てきます。「なぜ」「どうして」と聞いてくることが多くなります。
個人差はありますが、お母さんを困らせることが多くなったのは、成長していることが原因です。
2歳前半には自己主張が最高に達します。同時に甘えたい心と自立の心が同時に出ます。 「いや」「だめ」「自分でやる」と言った言葉が増えます。
2歳後半には、自己主張しますが、次第に感情を抑えることを覚えてきます。
3歳には、個性が出てきます。「なぜ」「どうして」と聞いてくることが多くなります。
個人差はありますが、お母さんを困らせることが多くなったのは、成長していることが原因です。
66 年齢と発達 05/22/2014 21:12:00

4歳になると言葉の発達とともに考える力が付いてきます。
因果関係が分かるようになり、正しいと思うことを主張します。この時期になると、理屈なしの指示が通らなくなります。
また、友達同士で協力をする集団遊びが盛んになります。 相手の行動を予測して行動したり、顔を洗っていないのに「顔を洗ったよ」とごまかす知恵も付いてきます。
因果関係が分かるようになり、正しいと思うことを主張します。この時期になると、理屈なしの指示が通らなくなります。
また、友達同士で協力をする集団遊びが盛んになります。 相手の行動を予測して行動したり、顔を洗っていないのに「顔を洗ったよ」とごまかす知恵も付いてきます。
67 達成感 05/23/2014 23:55:00

国語や算数に比べて、理科の実験や図工、美術、体育が好きな子が多くいます。
その理由は、学習の見通しが分かるからです。実験や絵画、工作、など学習結果が見えるからです。
このことから、達成したい目標が明確だと、意欲的に取り組むことができます。 配慮することは、実現可能な課題を示すことです。
なんとかできそうな目標だと、子どもたちは意欲的に取り組みます。そして、出来たことに対して認めることで、次への意欲が高くなります。
その理由は、学習の見通しが分かるからです。実験や絵画、工作、など学習結果が見えるからです。
このことから、達成したい目標が明確だと、意欲的に取り組むことができます。 配慮することは、実現可能な課題を示すことです。
なんとかできそうな目標だと、子どもたちは意欲的に取り組みます。そして、出来たことに対して認めることで、次への意欲が高くなります。
68 あこがれ 05/24/2014 23:45:00

子どもは、大人と同様に、尊敬する人と出会うと、「あの人のようになりたい」と勉強したり努力するようになります。
スポーツ選手や芸能人、科学者など子どもにとって憧れている人やその気持ちを大切に受け止めてください。 成長する過程で、目標とする人が変わる場合もありますが、小さいときからめざす目標があることはすばらしいことです。
本や映画、社会見学などいろいろな人と出会う機会を大事にしてください。
スポーツ選手や芸能人、科学者など子どもにとって憧れている人やその気持ちを大切に受け止めてください。 成長する過程で、目標とする人が変わる場合もありますが、小さいときからめざす目標があることはすばらしいことです。
本や映画、社会見学などいろいろな人と出会う機会を大事にしてください。
69 子どもの悩み 05/25/2014 21:34:00
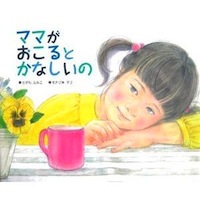
絵本『ママがおこるとかなしいの』を読みました。
学校で友達とけんかしたことをお母さんに話すと「あなたが悪いのだから、早くあやまりなさ」と言われ、 お父さんに相談すると「別のお友達と仲良くしたら」と言われます。
どうしても納得いかないので、おばあちゃんに悩みを話すと、ママやパパと違う答えが返ってきました。 おばあちゃんは「けんかして悲しんだね。本当は仲直りをしたいんだね」と声をかけられたことで、 けんかしたことを冷静に見つめ、自分の気持ちを聞いてもらった充実感を味わうことが出来たようです。
「しっかりしなさい」と言われるより「大変だったね」と共感された方が心が落ち着きます。 人は、怒りの裏側には、「悲しみ」「不安」「恐れ」を抱いています。 表面だけで判断するのではなく、心の奥にある感情を受け止め伝えることの大切さを作者は語っています。
学校で友達とけんかしたことをお母さんに話すと「あなたが悪いのだから、早くあやまりなさ」と言われ、 お父さんに相談すると「別のお友達と仲良くしたら」と言われます。
どうしても納得いかないので、おばあちゃんに悩みを話すと、ママやパパと違う答えが返ってきました。 おばあちゃんは「けんかして悲しんだね。本当は仲直りをしたいんだね」と声をかけられたことで、 けんかしたことを冷静に見つめ、自分の気持ちを聞いてもらった充実感を味わうことが出来たようです。
「しっかりしなさい」と言われるより「大変だったね」と共感された方が心が落ち着きます。 人は、怒りの裏側には、「悲しみ」「不安」「恐れ」を抱いています。 表面だけで判断するのではなく、心の奥にある感情を受け止め伝えることの大切さを作者は語っています。
70 感情と行動 05/26/2014 20:15:00

感情表現の抑圧は心の不健康につながります。感情を自由に表現させることで心を癒すことが出来ます。
「お姉ちゃんなんか死んでしまえ」と弟が言ったときに「お姉ちゃんが死ねばいいと思うほど、腹が立ったのね」とフィードバックして言い返してください。 この関わり方で、自分の気持ちを受け止めてくれたと安心します。
ただし、「お姉ちゃんが死ねばいい」と思う感情を行動に移したら大変な惨事となります。 感情は自由でも行動は制限が必要です。なぜなら、相手がいて相手を傷つけることは許されないからです。
子どもが乱暴な行動に出たときは、体ごと抱きしめて禁止させます。興奮が治まったら子どもの気持ちを聞くことです。
「お姉ちゃんなんか死んでしまえ」と弟が言ったときに「お姉ちゃんが死ねばいいと思うほど、腹が立ったのね」とフィードバックして言い返してください。 この関わり方で、自分の気持ちを受け止めてくれたと安心します。
ただし、「お姉ちゃんが死ねばいい」と思う感情を行動に移したら大変な惨事となります。 感情は自由でも行動は制限が必要です。なぜなら、相手がいて相手を傷つけることは許されないからです。
子どもが乱暴な行動に出たときは、体ごと抱きしめて禁止させます。興奮が治まったら子どもの気持ちを聞くことです。
